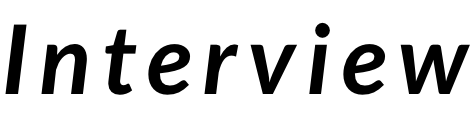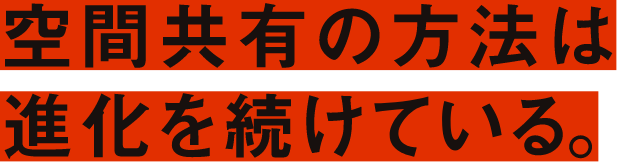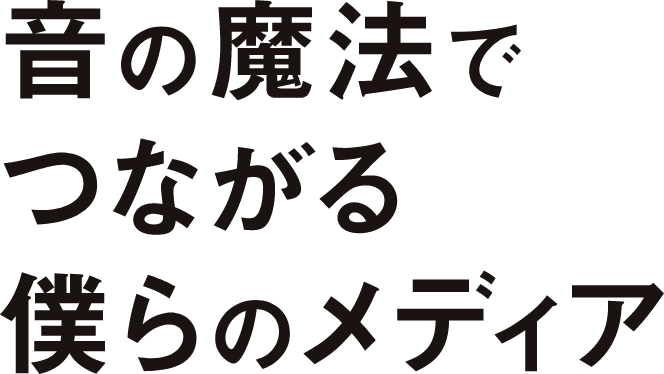
今年も「World OMOSIROI Award」の選考委員を務めた現“在”美術家・宇川直宏さんは、まだソーシャルメディアの黎明期と言われた時代にライヴストリーミングスタジオ「DOMMUNE」を開局。10年以上にわたり1万時間以上の番組を配信し、各国のアーティストの音と言葉を送り届けてきたパイオニア的存在だ。今回は、そんな宇川さんに、今注目を集める「音声」のメディアについて話を聞いてみたい。

1968年生まれ。現“在”美術家。映像作家、グラフィックデザイナー、VJ、文筆家など、マルチに活躍。2010年、ライヴストリーミングチャンネル「DOMMUNE」を個人で開局。ISCA国内映像コンテンツ部門審査員長、文化庁メディア芸術祭審査員、高松メディアアート祭ゼネラルディレクター、アルスエレクトロニカのサウンドアート部門審査員などを経験。今年、芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。

「音」のメディアを語るっていうお題をもらいましたが、僕はVJ(ビデオジョッキー)※の先駆者でもあるし、ミュージックビデオも100本はディレクションしてきたし、常に聴覚と視覚を結びつけることでメディアを作ってきた人間。にも関わらず視覚を遮断され、聴覚のみを考えるという大喜利は面白いかもしれない(笑)。うん、自分でもどんな話になるか想像がつかないけど、やってみましょう!
Clubhouse が話題になったように、たしかに、現在、音声メディアは注目を集めていますよね。メディア史を振り返ると、僕たちのコミュニケーションは「活字」→「音声」→「映像」という3 段階を経て更新されてきました。
具体的にいうと、15世紀中頃に、グーテンベルクによって活版印刷が発明されて以降、メディアは「新聞」→「ラジオ」→「テレビ」へと進化してきた。
さらに、家庭内で「音声」について考えると、1950年代末にオープンリールのレコーダーが登場し、60年代にカセットテープメディアが浸透すると、分娩室で赤ちゃんの第一声を録音する「産声レコード」というカルチャーが生まれた。並行して、8ミリフィルムの登場で、今度は赤ちゃんの動く姿を撮るようになり、70 年代以降にホームビデオが流通すると磁気信号で成長記録が収められた。どれも「音」→「映像」という流れをたどってるでしょ? 現代では、TikTok がリアルタイムでエフェクトを加えられるように、AR・XR といった仮想現実をクロッシングできる映像表現まで一般化。時代は「一体、現実って何?」というポストリアリティの探求まで到達してしまったわけです。
※VJ(ビデオジョッキー)…コンサート会場でリアルタイムで映像を組み合わせ、操作する人。宇川さんは1988年〜始めた。

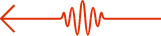
ライヴストリーミングスタジオ
SUPER DOMMUNE
ソーシャルメディアの夜明けと言われた2010年、国内でいち早く開局したライヴストリーミングチャンネルスタジオ兼、チャンネル。以来、世界中のDJやアーティストから絶大な支持を受け、配信番組は延べ約5,000番組、視聴者数は1億人超。現在は「SUPER DOMMUNE tuned by au 5G」に進化し、渋谷パルコ9階に公開収録スタジオを構える。
≫毎週月〜木曜の19時頃に配信。https://www.dommune.com
ところが今、「映像」から「音」のメディアに逆行する現象が起きているんです。理由は明確で、日常的なコミュニケーションに使うには、映像では情報量が多すぎるから。昨年、リモートワークが主流になり、Zoomが爆発的に普及したけど、同時に「Zoom疲れ」という現象が起きちゃった。見るだけじゃなく見られる行為って、負担が大きいですよね。Zoom飲みが定着しなかったとおり、会議や授業など特別な会合ならまだしも、日常的に映像を使うのはプライバシーの公開につながるので荷が重い。だからこそ、必然的に音声メディアに退行していくわけです。
あと、音を取り巻く状況で言うと、近年のサブスクリプションの台頭は大きな変化。お金さえ払っておけば無限に音楽を聴ける仕組みは、水道やガスや電気と一緒でしょ? 音楽はもう水みたいなものだとも言える(笑)。
ここで、一応Clubhouse がバズった理由を押さえておくと、招待制であるという閉鎖的な性質にも関わらず、話し手と聴き手の関係性がフラットになっていて、聴き手が突然スピーカーになれるというフリースタイルが新しいこと。Clubhouse は音声メディアとして、語る立場と聴く立場が反転したり、入り乱れたりする面白さ、コミュニケーションの新たなスタイルを提示できたんです。また、コロナ禍以降、ソーシャルディスタンシングが強いられて、会話や雑談の価値が高まったことも大きいでしょうね。
音への逆行は、実は今に始まったことではありません。それが電話ですよね。50年代のSF映画には、よく近未来の「テレビ電話」が登場しますが、面白いのは、その世界にはもう音だけの電話が存在していないこと。SFの世界では、映像から音への逆行は起きないんですね。でも、実際にFaceTime やZoom を使うようになった僕たちは、やっぱり電話を使っている。そればかりか遠隔コミュニケーションは、メールによって「音声」→「活字」へとさらなる逆行を果たし、加えてLINEによって、形式にとらわれないよりカジュアルな活字のコミュニケーションへと退行的進化を遂げました。
話を戻すと、Zoom疲れを経験したことで、かつて思い描いたテレビ電話が、ミーティングのプラットフォームとして台頭したにも関わらず、実は「会う」ことの本質とはかけ離れていたことに僕たちは気づいてしまった。僕自身もそうだけど、コロナ禍で「会う」とは顔を向き合わせることではなく、「空間を共有すること」だと肌身で感じた人は多いんじゃないかな。
それからテレビをつけていても耳で観る感覚ってあるでしょ? 耳だけで「ながら見」する感覚。これは、コミュニケーションの軸が映像ではなく、音声信号によって成り立っていたことの証明なのではないかと。僕は、VJやミュージッククリップを作っていた時代から既に、メディアにおけるコミュニケーションは音ありきで、そこに映像が付随しているというイメージを持っていて。だから、メディアが成熟した後に戻ってくる場所は、結局音なんだと思います。ちょうど今、「活字」→「音声」→「映像」と、ようやく一巡したところなのかもしれませんね。

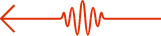
2021.2.23
World OMOSIROI Award 7th
ナレッジキャピタルからOMOSIROIの価値を発信する国際アワード。7回目を迎えた今年は、台湾のデジタル大臣オードリー・タン氏、京都大学特定教授の川上浩司氏らが受賞。
https://kc-i.jp/activity/award/omosiroi/
僕が2010年に始めた「DOMMUNE」には、コミューン(commune)のネクストレイヤーという意味が込められています。アルファベットで「C」の次は「D」、だから“D” OMMUNE。コミューンは、1960年代末のヒッピー文化に端を発する共同体のこと。既成社会の制度を否定し、家族に変わる概念のもとでコミューンを作り、集団生活をして、子どもは皆で育てるし、畑の収穫も皆のもの。所有から解き放たれた無政府状態の共同体である彼らは、ベトナム戦争反対運動やサイケデリックムーヴメントを背景に、カウンターカルチャーとして「フェス」の原型を作り上げた。きっと中心に音楽があったからこそ、多くの人がひとつの思想を共有できたのだと思います。僕は、そうした音楽で連帯したコミュニティをサイバースペースに作れないか、という発想で、SNSの夜明けと言われた2010年にDOMMUNEを開局しました。



世界各国から著名な
アーティストがDOMMUNEに集まる。
世界各国から著名なアーティストがDOMMUNEに集まる。
上:ニーナ・クラヴィッツ(数々の受賞歴を持つロシアのDJ)/下:デニス・ボーヴェル(東カリブ海の島・バルバドス出身のマルチプレイヤー)。
メディアの変遷が逆行するほどに成熟した今、これからは「空間を共有する行為をいかにアップデートするか」という時代。例えば、僕も関わった渋谷の「デジタルツイン」、つまり渋谷と瓜二つの仮想空間を作るプロジェクト「バーチャル渋谷」もそう。初歩から説明するとすれば、現実世界を仮想化した空間は「メタバース」、特に現実をそっくりコピーしたものは「ミラーワールド」といって、今、世界中のテック系企業がしのぎを削る分野。次なるコミュニケーションのプラットフォームは「メタバース」や「ミラーワールド」の中に生まれているとも言えます。とはいえ、物理空間とは全然違うでしょ? って思うかもしれないけど、現実世界をコピーした「デジタルな双子」の体感は近い。渋谷くらい国民的な街になると、訪れた経験のない人でも、スクランブル交差点や109など、具体的なイメージを持っています。また訪れたことのある人は「買ったばかりのエアマックスをチーマーに盗られた!」みたいなフィジカルなエピソードを持っているわけで(笑)。そうした個々人のイメージが集まり、ノスタルジアが交差することで、ものすごいリアリティを伴った空間が立ち現れてくる。このとき重要な鍵を握るのが「公共」かつ「有限」であることだと考えられます。
ここで面白いのが、昨年4 月にラッパーのトラヴィス・スコットが人気ビデオゲーム『フォートナイト』の中で行ったヴァーチャルライヴ「Astronomical」。
同時接続数1230 万を記録し、フェスの形を更新したとも言える事件だったんだけど、よく考えたらこのライヴは「メタバース」の空間でデータファイルが再生されている構造です。なのになぜライヴ的没入感を得られたのか? 何千万の人々が熱狂できたのか?
360度のVR空間『フォートナイト』では、トラヴィスの背中側や股の下からもライヴを体感することができる一方で、まったく同じ場所からもう一度観ることはほぼ不可能に近い。映画館で「隣の人のいびきがうるさくて集中できなかった!」という思い出や「このシーンで彼女の手を握った!」と一緒で、周囲との関係も含めて、2 度と同じ体験ができない。これによりライヴ感が生み出され、体験の意味を更新したわけです。つまり、このライヴには2つのVR空間がある。一つは何でもありの「メタバース」の世界。無限の広野が広がり、空も飛べて、海底でも呼吸ができる世界だと、約束事がないからこの空間を“新しい現実”として共有することができる。もう一つは、何かに付けて物理世界の制約と連動している「有限」の空間。ここでは「公共」としての“既にあった現実”を共有することが連帯を生むきっかけになる。このライヴでは、メタバースの世界にありながらも、公共で有限であったからこそ、個々のイメージが重なり合い、リアリティを伴う空間ができたのだと思います。

UKAWA NAOHIRO
Photo by Toshio Ohno(L MANAGEMENT)
WIRED Japan Vol.38
僕は、ヴァーチャルであろうとフィジカルであろうと、この公共で有限な空間に「音」を投じることこそ、コミュニティを豊かにする秘訣だと思っていて。たとえば、目の前の料理を味わう。味覚は共有不可能な領域なんだけど、同じ料理を同じ時間に同じ空間で食べることによって、体感を重ね合わせることができる。例えばそこにロマンティックな音楽がかかるだけで感動的な体験は増幅されるでしょ? 音楽は「公共で有限な体験」を「幻想で無限な体験」に広げる役割を果たしてきたと思うんですね。しかも、音楽には微細な感動を共有する力もある。視覚を「ピンクとオレンジと黄色の間の感動」と言語化しても伝わらないけど、音楽なら共有できる。抽象的な感覚さえも心の触れ合いの糧にして、自己と他者というハードルを一瞬で縮める音楽の力。物理空間でもヴァーチャルリアリティ空間でも、人と人とのつながりを豊かにするための「幻想」で「無限」の魔法だと思うのです。
宇川さんが出演したFM
COCOLO「OMOSIROI RADIO」の放送後、「音」をこよなく愛するおふたりに、細かすぎて伝わらない?音の楽しみを語ってもらった。

左)野村雅夫/右)宇川直宏
最近どんな音を聴いてる?
野村:めちゃめちゃ面白い〜!”音“となると、僕はやっぱりラジオ。今は世界中のラジオを聴けるから、コンゴのヒットチャートをチェックしたりね。
宇川:それ、最高! ラジオだからこそ、ケニアのトークのグルーヴとかもわかっちゃうわけでしょ?
野村:そうそう。ラジオはその国の文化が全部出ちゃうわけで。聴きながら妄想海外旅行も可能(笑)。
今、気になる音をひとつ挙げるなら?
宇川:まさにそう。本来排除すべきノイズが、リアリティを増幅させる。今気になるのは、雑踏の音かな。
野村:先に言われたな(笑)。うーん、あえて挙げるなら、映画のチープな効果音。僕は映画批評もするので、もっとこだわってほしいと思っていて。
宇川:わかる!昔からある「ライヴラリーもの(フリー素材)」にも、面白いものがあるんだけどね。
野村:そうそう! でもそれも普通に使うのはちょっとね。もっとチャレンジしてほしいな!
FM COCOLO HOLIDAY SPECIAL
2/23(火・祝)、FM COCOLOと「World OMOSIROI Award 7th」がコラボレーションし、3時間にわたる生放送が実現! 選考委員・宇川直宏さんと菊地あかねさん、そしてDJ・野村雅夫さんがOMOSIROIを語り尽くした。リスナーのOMOSIROIエピソードや受賞者・選考委員による意外な選曲も大反響◎
- 出演者
現“在”美術家 宇川直宏
アートディレクター/アーティスト 菊地あかね - DJ 野村雅夫