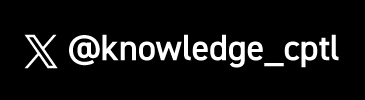サロンイベントレポート
木曜サロンレポート
- テーマ:
- 【“なぜ誰も思いつかなかったのか”をカタチに】救命現場を変える映像通報システムLive119
開催日: 2025年3月6日


○活動の主旨、目的○
株式会社ドーンの宮崎社長・取締役の古野さんをお招きし「Live119」という救命用の通報システムの開発や営業手法についてお話いただいた。
救急隊の現場で聞く「あったらいいな」というアイデアは、行政や大企業の力だけでは実現しないことが多く、ドーン社は商品開発からロビーイング、現場への導入に至るまでを一気通貫で行うことで、現場主義のサービスを開発するに至ったという。
しかし、サービス開発までの道のりは非常に長く、現場の声を拾い上げてプロトタイプを作り、現場の反応を確認し、そこから消防の上層部に売り込みをして承認を得たのちに、ようやく実証実験を開始できる。実証実験で上層部が納得するパフォーマンスを出せなければ導入は決まらないとのこと。
宮崎社長曰く、この長い段階を踏むためには、「熱意」がカギになり、消防や警察は市民の命や安全を預かる現場だということを理解し、現場で働く人々と同等の熱意を持った時に突破口が開いたとお話しされた。
「売上ばかり追っていたときは恥ずかしながら赤字でした。”自分たちのサービスが現場を絶対によくするんだ”という信念を持てるかどうかが大切」と締めくくられた。
ナレッジドナー(知の提供者)プロフィール
古野 直樹 氏
株式会社ドーン顧問・古野電気株式会社オーナー家

祖父が創業した船舶用電子機器メーカー古野電気(株)に入社。主に海の技術を陸上に応用する新事業開拓や商品企画に従事。一例では狩猟業界向けにGPSドッグマーカーを企画。個人的にも狩猟免許を取得し、現在も猟師の知見を活かしながら企画開発を続けている。ハードウェアとクラウドサービスは、連携でもっと便利になるという想いから、古野電気とも関わりながらクラウドサービスを得意とする(株)ドーン顧問に就任。
宮崎 正伸 氏
株式会社ドーン代表取締役社長

大学卒業後、(株)オービックを経て、当時創業期であった地理情報システムに係るソフトウェア開発に強みを持つ(株)ドーンに入社し、官公庁やインフラ系企業向けの営業に従事。副社長就任後、普及前のクラウドにいち早く着目し、クラウド事業に進出する。社長就任後は祖業のライセンス事業からクラウド事業に軸足を移し、警察・消防等といった官公庁向けの安全安心分野のクラウドサービスの拡販に注力するほか、エッジAI技術を活用した新サービス創出に向け邁進中。
ナレッジドナーインタビュー

- 実際にLive119を導入した現場ではどのような反応が見られましたか?
-
宮崎氏:
「おかげで人命が救われた」「状況を正確に把握できたおかげで、現場に早く到着することができて助けられた」など、人命救助に直結する肯定的な反応が多いと感じています。
消防車や救急車は、要請してから現場に到着するまでの所要時間が平均8〜10分と言われており、その短い時間でどこまで情報を明確化して事前準備を整えられるかが重要になってきます。
従前の救急要請のような口頭だけでのやり取りでは、例えば相手方の言う『青い』という情報に対しても『何が青いのか』を確認する必要があり、そういった情報の擦り合わせだけで数分を費やしてしまうことがありました。
一方、Live119は傷の深さや状態を目視で素早く把握して、移動中の救急車内で適切な医療器具を事前に準備できるため、到着後の対応がよりスムーズになります。こうした点で、映像通報システムを救命現場に導入することにより、救急車内の事前準備の仕組み自体が大きく変化したと感じています。
古野氏:
まさに、「百聞は一見に如かず」というような世界ですね。 - 「誰も思いつかない新しいアイデア」を実現するにあたり、特に心がけていることがあればお聞かせください。
-
宮崎氏:
気をつけていることは、「自分本位にならないこと」です。何かを開発するとき、人はどうしても自分にとって都合の良いように考えてしまいがちですが、実際の現場では必ずしもそれが良いとは限りません。
例えば、消防関係者向けの開発を行う場合、彼らが直接向き合っているのは救助する人々です。そのため、開発においても「消防隊員にとって便利か」だけではなく、「救助される側にとっても本当に役立つものか」という視点を常に意識するようにしています。
かつて、「自分が怪我して気が動転している時に、画面の拡大縮小ができるのか?」と、言葉を掛けられたことがあります。実際の緊急現場などで気が動転してしまっている時は、普段なら簡単にできるようなことでもできなくなってしまうことがあるという例えです。考えてみれば当たり前の事ですが、気が付かない視点でもあります。
こうした点を踏まえ、自分本位な開発にならないようにするためにも、必ず複数回の実証実験を行うようにしています。1回目では自分が良いと思った想定が実際のニーズと大きくずれていたり、現場の方々が求めるものとは異なっていたりすることが多々あるためです。2回目の検証からが勝負になってきます。
試行錯誤を重ねながら改良を続け、アイデアをより実用的なものに仕上げていけるように心がけていきたいです。
※木曜サロンレポートはナレッジサロン会員さまを対象としたイベントのレポートです。
木曜サロンとは
幅広い「知」に出会える、気付けるちょっと知的な夜、展開中。
ナレッジサロン会員様を対象に、毎週木曜日の夜に開催。幅広い業種業界から「ナレッジドナー(知の提供者)」としてゲストスピーカーを招き、専門知識や経験、取り組んでいるプロジェクトや生活の知恵まで幅広い「知」を提供。参加者同士の交流や会話を尊重し、自由で気楽な会話を中心としたカジュアルなサロンです。