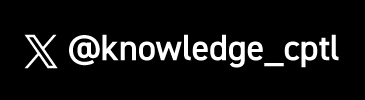サロンイベントレポート
木曜サロンレポート
- テーマ:
- 哲学サロン -対話の力を実感する-
開催日: 2025年5月15日


○活動の主旨、目的○
「哲学対話」を一言で言うと「探求的な対話」。会話によって探求することが目的であり、哲学対話のニーズがあるのか、探求のために「会話」というツールが使われているのか、探求があるから対話ができるという状況なのか・・・ということが最近気になっているが、結論としてはどちらでも良いとお話された。
その後は鈴木氏を含む参加者全員で対話のテーマ「探求とはなにか?」について順番にお話された。
「最近ChatGPTを使い始め、様々なことを教えてくれるため興味があればChatGPTに聞いている」「飽き性で探求するということが苦手」「自分は仲のいい人とうまくやれているのかなと思っているので自分自身を探求していると思う」など、探求についての様々な対話がされた。2周回って対話は終了したが、2周目は他の人の話を聞き、触発されて対話される方や1周目では話がまとまらなかった方が2周目はまとめました!と笑いを誘いながらお話されるなど、各々の個性が光る対話で終了した。
ナレッジドナー(知の提供者)プロフィール
鈴木 径一郎 氏
大阪大学 社会技術共創研究センター 特任助教

大阪大学文学研究科博士後期課程(臨床哲学)単位取得退学。
哲学プラクティショナー。「社会の中で生きる哲学」を探求する、カフェフィロ副代表。
大阪大学社会技術共創研究センターで、多数の企業との「責任ある研究・イノベーション」に関する共同研究に従事しながら、並行して、地域づくり・企業文化形成・学校教育・医療福祉ケアなどのさまざまな文脈で、哲学対話のファシリテーションを中心とした、現場ごとのアクターとの共創による哲学実践をおこなっている。
ナレッジドナーインタビュー

- 哲学を始められたきっかけをお教えください。
-
大阪大学の文学部に入学した時点では何を研究したいか決めておらず、歴史について研究しようかなと考えたこともありました。大学には臨床哲学研究室というとても変わった研究室があります。そこに所属する先生方の哲学の授業を受講した際に、アートパフォーマンスのビデオを鑑賞するというような内容が多く、「ここなら何でも自由に研究できそうだな」と感じて、臨床哲学研究室を志望しました。
自由に研究をしたくて志望したところが偶然哲学の研究室でもあった、という感じですね。始めから哲学を学びたかったとか、何かの出来事をきっかけに哲学を学ぼうと決意した、ということではありませんでした。 - 今後の展望をお聞かせください。
-
本日の講演のテーマは「探求」でしたが、思い返せば私は大学の臨床哲学研究室に入った当初から、”探求を独占しない”ということを自分のテーマにしていました。
”探求の独占”を映画制作で例えるなら、監督だけが考えてほかのスタッフや役者に考える余地を与えないような。
面白くないですよね。
専門家やある種の権威ある人だけが探求することを独占してしまうことが嫌で、どの立場にある人も色々なことを考えて実験できるほうが面白い、という考えがずっと根底にあったのです。
哲学に限らず、誰もが色々なことを考えて探求し、あるいは探求しないことにも互いに敬意を持てるような世の中になっていったらいいなと考えています。
あえて哲学という領域に限定して語るなら、哲学のようなものへの参入障壁を下げるというか、すでにしていることを「している」と言える人が増える方向に寄与できたらいいなと思っています。
※木曜サロンレポートはナレッジサロン会員さまを対象としたイベントのレポートです。
木曜サロンとは
幅広い「知」に出会える、気付けるちょっと知的な夜、展開中。
ナレッジサロン会員様を対象に、毎週木曜日の夜に開催。幅広い業種業界から「ナレッジドナー(知の提供者)」としてゲストスピーカーを招き、専門知識や経験、取り組んでいるプロジェクトや生活の知恵まで幅広い「知」を提供。参加者同士の交流や会話を尊重し、自由で気楽な会話を中心としたカジュアルなサロンです。