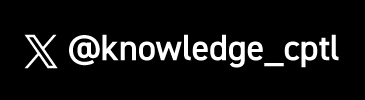サロンイベントレポート
木曜サロンレポート
- テーマ:
- 聴こえの仕組みと難聴 -究極の臓器 “内耳” とは!?-
開催日: 2025年7月31日


○活動の主旨、目的○
人口の1割が罹患しているという難聴。これは糖尿病の患者数に匹敵し、歳を重ねるごとにその割合は増加するという。中年期の難聴は認知症のリスクを高め、さらにうつ病や社会的孤立を引き起こす原因となる。
これらの背景から、難聴は超高齢化社会において非常に重要な問題となり、難聴を予防・治療することが生活の質向上や脳の健康に繋がるカギであり、また、難聴は言葉の獲得に大きな影響を与えることから子どもにとっても深刻な問題で、早期の対応が必要なため音が聴こえる仕組みを理解することが重要となるとお話しされた。
音は外耳から中耳を通り内耳の蝸牛に届き、蝸牛で音の振動を電気信号へ変換し脳へと伝えている。蝸牛には感覚上皮帯があり、この感覚上皮帯では音を伝える「変換器」と小さな音の振動を増幅する「増幅器」役割を担っているため、蝸牛は 「ミクロな精密部品」がつながったシステムといえるとのこと。
代表的な難聴のほとんどは内耳蝸牛が障害されることによるものだが、原因が十分にわかっていないため、今後さらに研究を進め、難聴だけでなく難聴が引き起こす脳疾患を減らしていきたいとお話された。
また、現在は民間療法で行われている音や聴覚刺激による予防法・治療法を研究し、メカニズムを解明することで民間療法を未来医療にするという試みや、体の状態を知ることのできる窓口である「感覚」の状態を測ることによって、脳や他の臓器の病気を素早く診断することができないかという基礎研究も始まっているとのこと。
このような研究を続けていくことで薬を使わない治療ができるようになる可能性があり、聴覚研究は心豊かで幸せな未来の健康社会の実現に向かって、非常に重要であると締めくくられた。
ナレッジドナー(知の提供者)プロフィール
日比野 浩 氏
大阪大学大学院医学系研究科 薬理学講座 教授
大阪大学国際医工情報センター センター長

1994年 大阪大学医学部を卒業後、同大学耳鼻咽喉科に入局。
1999年には大阪大学大学院医学系研究科博士課程(耳鼻咽喉科学)を修了。
同年より大阪大学大学院医学系研究科薬理学講座助手、その後1999年から2002年まで米国ロックフェラー大学にて研究員を務める。
2007年には大阪大学大学院医学系研究科薬理学講座准教授に就任。
2010年からは新潟大学大学院医歯学総合研究科分子生理学分野教授として研究と教育に携わり、2021年より現職である大阪大学大学院医学系研究科統合薬理学教授として現在に至る。
ナレッジドナーインタビュー

- 難聴の研究を志したきっかけについてお聞かせください。
-
20数年前に耳鼻科医として働いていた時、難聴の患者様をしばしば診てきたのですが、当時の薬や治療法ではなかなか治らない方が多くいらっしゃいました。
この状況を解決するためには、難治性難聴の原因に大きく関わるとされる「内耳」について基礎研究をして、内耳の障害について理解しなければならないと思ったことがきっかけです。 - 加齢による聴力低下を予防するためのアドバイスがあればお教えください。
-
歳を重ねると誰もがある程度は難聴になってしまいますが、予防策の一つとして、「大きい音を長時間継続して聴かないようにする」というものがあります。
例えば、ヘッドホンやイヤホンを経由して大きな音を再生する際、スマートフォン等のタイマー機能を活用して、一定時間で再生を区切るようにするなど工夫してみてください。このような「聴覚の保護」を若いうちから心掛けることが、加齢性難聴の加速を防ぐ一つのポイントになると思います。
※木曜サロンレポートはナレッジサロン会員さまを対象としたイベントのレポートです。
木曜サロンとは
幅広い「知」に出会える、気付けるちょっと知的な夜、展開中。
ナレッジサロン会員様を対象に、毎週木曜日の夜に開催。幅広い業種業界から「ナレッジドナー(知の提供者)」としてゲストスピーカーを招き、専門知識や経験、取り組んでいるプロジェクトや生活の知恵まで幅広い「知」を提供。参加者同士の交流や会話を尊重し、自由で気楽な会話を中心としたカジュアルなサロンです。