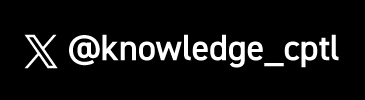サロンイベントレポート
木曜サロンレポート
- テーマ:
- 仲間をシアワセにするDXとは? ――大阪大学の挑戦と未来
開催日: 2025年9月18日


○活動の主旨、目的○
「日本DX大賞2025」業務変革部門で大賞を受賞した大阪大学のDX、OUDXについてお話いただいた。
大阪大学では、日本の大学が直面する課題を解決するため、3つのプロジェクトを柱にDXを推進している。
まず1つ目の「OUIDプロジェクト」は、学生・教職員、地域コミュニティなど大学に関わる全ての方に統合IDを提供し、付加価値の高いサービスを提供するというもの。顔認証による入退館や図書の自動貸出など、大学では国内最大級の社会実装に向けた取り組みである。また、現役学生と教職員向けに導入された「デジタル学生証・教職員証」は学生証の表示のみならず時間割や連絡バス時刻表など、利用者にとって便利な機能を集約したスーパーアプリとなっている。
2つ目のプロジェクトは「OU人財データプラットフォーム」で、OUIDを基盤に大学の人的資本を集約・共有・連携・共創し、教育・研究・経営に役立てるもの。学生の履修計画やキャリアサポートだけでなく、卒業生との繋がりを維持することでリカレント教育や寄付金募集につなげることもできるとのこと。
3つ目の「業務DX・人財育成プロジェクト」では、RPAや生成AIなどを積極的に導入し、業務の生産性向上と職員のITリテラシー強化を図っている。これにより、業務の質向上や効率化だけでなく、内製開発によるコストの削減も実現した。
これらのDX推進にあたり、「ヒト」がいない、「カネ」がない、「戦略」がわからない、「組織の動かし方」がわからないという課題に直面したという。
「ヒト」不足に対しては、部門や職位の壁を越えて「大学を変えたい」という有志の仲間を集め、「楽しい」施策、「学び」の場を用意することで協力の輪を広げた。
「カネ」がないという課題では、ベンダロックインの排除など、既存のプロジェクトやシステム運用のコスト構造を見直し、2年間で約5億円のコスト削減に成功。この資金をDXプロジェクトに充てることができたとのこと。
「戦略」については、DXを「ITツールの導入」ではなく、新しいIT技術が大学の教育・研究・経営にどう貢献するかを分かりやすく「翻訳」して伝えることが重要であると考え、「基盤整備」「先進大学との同質化」「差別化」という3つのシンプルなステップで示し、学生や教職員にとってメリットのあるシステムづくりを進めている。
そして、「組織の動かし方」については、信頼関係を築くための対面コミュニケーションを重視し、「小さく創って大きく育てる」という方針で、DXのメリットを一人ひとりに丁寧に説明し、理解と協力を得る必要があるとお話された。
最後に、今後はまず基礎整備を固め、世界の先進的な大学に学び、追いつくことを目指す。そして、大阪大学ならではの強みを活かしたDXを実現し、将来的には他大学や研究機関へシステムを提供。「システムの共創」を通じて、日本の大学・研究機関全体の国際競争力強化に貢献していきたいと締めくくられた。
ナレッジドナー(知の提供者)プロフィール
鎗水 徹 氏
大阪大学 OUDX(OSAKA UNIVERSITY DIGITAL TRANSFORMATION)推進室 教授 (副室長)

大阪大学OUDX推進室 教授 (副室長)(以下兼任、D3センター教授、情報推進本部 教授、大学院情報科学研究科 教授、キャリアセンター 教授、中之島芸術センター 教授)。大阪大学のDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進リーダーとして、大学全体の教育・研究・経営のDXに従事。
新日本製鐵(現 日本製鉄)入社後、約30年間のIT業界のベンダー・ユーザー企業両方での実務経験を踏まえた、「経営とIT」戦略の理論研究と実践に取り組んでいる。早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程 単位取得満了。
経営情報学会 役員(研究担当)、日本経営学会、組織学会、教育システム情報学会 会員。
ナレッジドナーインタビュー

- DXを導入するにあたり、乗り越えるべき課題は何だとお考えですか。
-
現在のAIは誤った情報を生成することもあるので、正しく活用するためのガイドライン策定等は必要だと思います。ただ、これは私にとってはかつて何度も見た景色で、WikipediaやGoogle検索のリリース当初も、インターネット上に出てくる情報が必ずしも正しいとは限らず、様々なバイアスが入っていました。それらと今の生成AIは似たような状況なのかなと感じています。
現状、様々な課題はありますが、遅かれ早かれDXが前提となる世界に必ず変化していきます。AIを活用するメリットとデメリットをきちんと理解して、今のうちから「とにかく使ってみる」ことがやはり大事だと思います。
スマートフォンも当初はおもちゃのようだと言われていましたが、今では多くの方の必需品ですよね。初めは何でもそういうものだという前提で、DXも使える人がどんどん使って仲間を増やしていけば良いのではないかと思っています。 - 今後の展望をお聞かせください。
-
本日お話しした「大学間で共用する」ことのモデルにしているのは、いわゆる「全銀システム」と呼ばれる、日本国内の金融機関の間で資金決済を行うための大規模なオンラインシステムです。
ほかにも、今は運営会社の異なるコンビニへ納品する商品を一つのトラックでまとめて運送する「共同配送」が運用されており、これらのように、同じ業界内での競争する部分と連携する部分を上手く使い分けるシステムを大学間でも構築したいと思っています。
国内に約800ある大学の多くが、今後運営が苦しくなることは目に見えています。だからこそ、今後は大学が本来持つ教育や研究の強みに投資の比重を置く必要があると考えています。実際、関東の大学間では、一つの大学所属の講師が複数校の一般教養の講義を受け持っている例もあります。
このように、共用できる部分は共用して、大学独自の強みの部分により一層力を注ぐことができなければ、今後生き残っていけません。そしてそれをどう実現してくのかという部分で、たとえばITを活用した単位互換システムや、IDを連携した仕組みなどを構築し、希望する大学に提供していきたいと考えています。共存できる部分は共存して、日本の大学の国際競争力を高めていきたいです。
※木曜サロンレポートはナレッジサロン会員さまを対象としたイベントのレポートです。
木曜サロンとは
幅広い「知」に出会える、気付けるちょっと知的な夜、展開中。
ナレッジサロン会員様を対象に、毎週木曜日の夜に開催。幅広い業種業界から「ナレッジドナー(知の提供者)」としてゲストスピーカーを招き、専門知識や経験、取り組んでいるプロジェクトや生活の知恵まで幅広い「知」を提供。参加者同士の交流や会話を尊重し、自由で気楽な会話を中心としたカジュアルなサロンです。