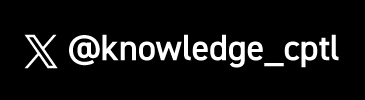VisLab OSAKA


「情報」をアート&デザインでわかりやすく
わかりにくい「情報」をアートとデザインを使って、わかりやすく見せる[“Visualization”(ビジュアリゼーション、可視化)]。
それがVisLab OSAKAの目指すもの。

VisLab OSAKA/ビジュアリゼーション
ラボラトリー大阪
インタビュー
先端技術が交流の柱になる
コラボレーションコミュニティ

大阪大学
サイバーメディアセンター教授
下條真司氏
ナレッジキャピタルの企画とともに誕生。
:ザ・ラボに参画された目的を教えてください。
まずはVislab Osakaについて説明しましょう。ザ・ラボという場をもつナレッジキャピタルが掲げる、新たな価値を創造するというコンセプトに私達は企画段階から賛同しており、多彩な研究機関や大学と産学連携と共同研究の元、グランフロント大阪開業時には情報通信研究機構(NICT)、関西大学、関西学院大学、大阪電気通信大学、バイオグリッド関西、臨床医工情報学コンソーシアム関西、サイバー関西プロジェクト、そして私が所属する大阪大学と共同でコラボレーションオフィスをナレッジキャピタル内に立ち上げました。それがVisLab Osakaです。我々のオフィスは上層階にもあるのですが、ザ・ラボが掲げるコンセプトにももちろん賛同し、ブース展開させてもらっています。
:具体的に、この場でどういった活動をされてきましたか?
ザ・ラボでは、参画している様々な大学や団体との連携とその活動の広報、プロトタイピングと展示によるフィードバックを通じた研究開発を行っています。多様な研究機関が参加しているのと同様、活動の分野も多岐にわたり、AR、ロボット、宇宙、スパコン、創薬etc…とてもひとことでまとめられるものではありません。一方で大事なのが、ここで学生に研究を説明させることで、狭い研究室の中にこもるのではなく、各研究は実際に一般の人にはどのように見えているのか、また、どうすれば伝わるのか、という点を学ばせる、人材育成の場としての機能も大きいですね。


「可視化」が目指す未来の研究開発。
:展示や活動を通じて、期待していることって何ですか?
私達の研究、つまり科学技術やそのプロトタイプを見せることで広く一般の方々にその内容を広めることです。一見すると大学や研究機関の研究はわかりにくいものが多いのですが、それをいかに可視化して、一般市民に見せ、またその研究開発の過程に参加してもらうようにするか。そしてこの可視化というキーワードはもうひとつ意味があり、いわゆるスーパーコンピューターの計算結果の視覚化、という意味もあります。研究の内容にもよるのですが、そういったふたつの可視化をキーワードとした市民参加型の研究開発を進めていきたいと思っています。言葉にすると難しく感じるかもしれませんが、展示は研究者や学生が見せ方も含めてわかりやすく工夫したものがほとんどですので、気軽に体験に来てほしいと思います。