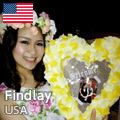カトリック教の国ポルトガルでは、諸聖人の日である11月1日は、祝日です。 教会ではミサが行われ、お墓参りをし、墓石の前に花を供える家庭もいらっしゃいます。
お墓といえば、ポルトガルでは、十字架の前に棺桶が収まるサイズの墓石があるタイプが多いですが、リスボンのプラゼーレス墓地では、立派なものがものが並びます。石造りの家のようになっており、その中に一族の棺桶が収まるようになっています。
中には、写真のように石像の下に埋められている場合もあり、その人物がどんだけ家族に敬われたのか、あるいは権力の関係か、想像を巡らせてみたりして。
プラゼーレス墓地は規模が大きいので、墓のタイプ(設計、職業、著名人など)が分かるように、入り口に案内のようなものが置かれています。それぞれゾーンで分けられてたり、墓の前にそれぞれの印が付けられている場合もあります。

立派な墓の数々

石像の墓

マップ。 3番は、フリーメイソン
さて、諸聖人の日の祝日ですが、私が住んでいる地域では、朝から子どもたちがパン入れの袋を持ち、町内の家々の前で、「Pão por Deus(パン・ポル・デウス=神からの恵であるパン)」と叫び、お菓子をもらいます。 本来は、さつまいもから作られるブロアという種類のパンをもらう習慣だったのですが、お菓子を簡単に買えるのと、作るのが面倒であるからか、あまり見かけなくなりました。
(昔の記事にも書きましたが、)幸いにも私たちの地域では、いまだにPão por Deusをこの日に合わせて作るお年寄りがいますので、お菓子目当てに町内を回った息子が、このパンを持ち帰ることもあります。
私は今年、近くの女性からたくさんのPão por Deus を購入し、外国人の友達に分けてあげました。そして、子どもたちにはお菓子を用意。朝から甲高い声が聞こえ、大忙しでした。

伝統的な Pão por Deus

子どもたちへのお菓子の準備
なお、知り合いと話していて分かったのですが、リスボンの方では危険だからか、このしきたりはないそうです。その代わり、日本でもお馴染みの10月31日ハロウィーンの日に、親と一緒にアパート内のドアを叩いて、お菓子をもらうと言ってました。
また、リスボンに近い別の地域では、学校のお休みが、本来の11月1日ではなく、10月31日になったと聞き、驚きました。
世界がグローバル化し、どんどんと国・地域特有の伝統がなくなっていくのは、悲しいことです。
とはいえ、お菓子をたんまりもらえる諸聖人の日・ハロウィーンは、息子にとって上位に入る年間行事だそうで、私もアメリカ式に、息子とジャック・オー・ランタンをせっせと作り、ハロウィーンにちなんだ夕飯で子どもたちを驚かせたりして! 影響されやすいこと。

ハロウィーンのディナー