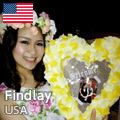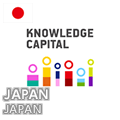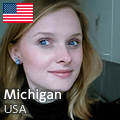「ドラゴン」を探すミッションは、旅早々に失敗だったと感じさせられた。モロッコという未知の地を、千夜一夜物語のようにミステリアスで不思議に溢れたところだと願うのは幼稚染みていて、「砂漠のドラゴン」などといった一話くらいあるだろうと考えていたナイーブな気持ちは直ぐに現実に戻された。街は神秘どころか、道路は人々も占領するほど秩序なく、街角のゴミは錯乱し、ゴミ捨て場は野良猫と野犬の大食堂と化している。魚を路肩に直接並べて販売しているのには驚いたが、基本、店の商品陳列はセンスや見やすさよりも数重視、外国人はカモにされ、強引、またはしつこく物を売られるし、売れる物なら片方だけの靴まで路上に並び、子供も物売りをさせられるといった、タフな生活感満載といった場所なのである。唯一、抱いていたイメージに当てはまったのは、町中に響くコーランと、乾いた空気に漂う香辛料の香りだろうか。そんな僅かなエスニック感にすがる気持ちで、いろんな路地を歩いたが、ドラゴンは見当たらなかった。

ファッション用品のディスプレイ方法が独特。

とにかく目一杯に商品が並ぶ。

魚の売り方には驚いた。
海の町アシラなら、タツノオトシゴのモチーフがどこかにあってもおかしくない。女性の手のヘンナ模様にないだろうか。場所を問わずマットを敷き、祈りを捧げる男性を何人も目にしたが、彼らの動きは竜に似てやしないか。異文化の色彩でさえ、竜に通じるものがあると思うのだが、注意を引く商品はどれもペルシャ絨毯をかけたラクダのマグネットである。壁の落書き、仕舞いにはテーブルのシミにさえ、それらしき形を求めたが、全く縁がなかった。意地になり、観光どころではなくなっていたので、「ドラゴンはきっと、モロッコの地には辿り着かなかったのだろう」と踏ん切りをつけ、探すのを一旦諦め、みんなと旅そのものを満喫することにした。

ヘンナで美しい模様をつける。

もしや辰の落とし子?!

ファティマの手は縁起物。

民芸品の色合いは、シルクロード的?!

ラクダのマグネット

誰もいない海で海水浴。地元の人に珍しがられた。水温は、ポルトガルよりも暖かかった。
12月31日。
年末になってもイスラムの土地では、新年の祝いをする気配は感じられない。
私たちはもう、迷わず街を歩き回れるようになっていて、日々のルーティーンとなったいつものカフェに向かう。前日と同じようにビサラという乾燥空豆のスープと、ハルチャなどといったモロッコ風パンやクレープをお馴染みのミントティーと一緒に注文する。通りすがりのショップは普段通り営業していて、いつもと何の変わりもない。

モロッコ風の朝食

モロッコのミントティー用に販売してる。
私たちは、街で唯一酒を売っている酒屋に向かい、モロッコ産のグレーワインというのを購入し、宿でしっとりと新年の乾杯をした。
1月1日。
1年間の邪悪を取り除くため、モロッコ式ハマムを体験。
ハマムとは、モロッコの伝統文化である大衆浴場のことで、日本と違うのは、浴槽風呂ではなく、温度差のある3つの部屋の蒸し風呂となっており、一番奥の部屋が高温で、出口に向かって部屋の温度が下がっている。体を流すためのお湯は、各部屋に蛇口が取り付けられており、そこで熱湯と水の温度調節をしながら、それぞれの大バケツに溜め、それを自分の陣取った場所に持って行き、手持ち桶でバケツからお湯を汲みながら体や髪を流す仕組みになっている。またハマムの特徴は、体や髪を洗う前に、スチームで温まった体を専用タオルでゴシゴシこすって、垢すりをすることだ。そのために、どのハマムにも垢すりやマッサージをしてくれるプロのおばちゃんたちが待機している。ちなみにハマムは大衆浴場とはいっても、日本みたいに素っ裸になる必要はなく、パンツは履いたまま入室しても良く、外国人はビキニの下の部分を履くケースが多いらしい。
私たちは、日本の銭湯グッズと同じようなセットを抱え、地元の人が利用するハマムに向かった。入り口で入浴料を払い、脱衣所で服を脱ぐところまでは、日本とほとんど変わらない。違うのは、脱衣場のカウンターで僅かな釣り銭で荷物を預かってもらうことと、靴を履いたまま脱衣所まで入っても良いこと。
まずは、同じカウンターで垢すりマッサージをお願いする。すると、カウンター内にいたおばちゃんが、私たちが服を脱ぐのと同じタイミングで裸になり始めるのだ。そして私たちが浴室に入る後ろから続き、最初の浴室の蛇口の横に、「ほれ、そこ」と指で指して、私たちのための場所を陣取ってくれた。オロオロとぎこちない私たちを横目に、巨大なバケツを足で蹴りながら蛇口の下に運び、そこに丁度良いお湯加減でお湯を張ってくれた。豪快な体をしたおばちゃんたちは、態度や仕草も豪快だ。バケツから汲んだお湯をばしゃんばしゃんと体にかけてくる。伝統的な黒石鹸(サボン・ノアール)という、焦茶色の水飴のようなものを体中に塗っておけと促され、叱られた子供のような気持ちでそれを塗りたくっている間、おばちゃんは隣の部屋に移動して、別のおばちゃんとおしゃべりを楽しんでいる。茶色い水飴を塗りたくった、汚らしい姿で、なすすべもなく体育座りで待っていると、大股でおばちゃんが戻ってきて、ドスンと真横に座り込んだ。事前に購入しておいた垢すりタオルを渡すと、私の腕をつかみ、それで力強くゴシゴシとしごくようにこすり始めた。すごい力なのだが、ものすごく気持ちが良い。もうやられるがまま、身も心も預け、全てを委ねた。おばちゃんは、自分のふくよかな体を台にして、私の体の各所から垢をこそげ出して行った。時々、脱力状態の私を、指でツンツン突き、
「ほれ、見てみろ!」
と誇らしげに、肌の上に広がる茶色い消しゴムカスのような垢を確認させられる。
「ワオ!すごい!」
笑ってきゃーきゃー騒いで、おばちゃんの自尊心をくすぐってあげながら、異文化、他言語での「裸の付き合い」を体験した。
この大衆浴場という場は、モロッコの女性たちの社会そのものであって、彼女たちが一番人間らしくいられる場所だと思う。
モロッコの街を歩いていると男性の視線を感じることがあるのだが、それは冷やかしではなく、ヒジャブなどで頭を隠さずに堂々と外を歩く私たちへの軽蔑的な眼差しであった。通りすがりに威圧的に罵ってくる男性もいる。
このように男性優位なモロッコでは、女性の立場は明らかに低く、女性はほぼ決定権がなく、どこか遠慮がちに見えた。
そんな姿に引き換え、どうだろう、蒸し風呂の女性たちはみんな本当に生き生きとしていた。一番奥の高温の部屋では、真っ白な蒸気をまとった女性たちが和気藹々、世間話や噂話に花咲かせている。そんな中、子供たちもバケツに浸かって遊んだり、はしゃいだりしていて、更にその場を賑やかにしていた。しかも驚くことに、裸の女性は次から次へと増え、座る場所がなくなるほど、浴槽は混み合っているのだ。
私たちは、持参した緑色のクレイパックを開けると、おばちゃんがすかさずそれを奪い取り、中身の匂いを嗅ぎ、
「これはいいものだ」と言わんばかりに、目を見開いて伝えてくる。自分の顔に塗り、指に残った分は首元に擦り付けた。そして気付けば、他のおばちゃんたちも我々と同じように顔を緑にしており、買ったばかりのクレイパックはあっという間に無くなった。そして、みんなでシュレックだとお互い指差して笑い合った。
全員胸が露わなのに全く違和感はなく、雲の上の裸族の世界に迷い込んだかのようだった。この世界の住民はみんな心の奥底から笑っている。
一年分の垢をこすり落とし、なんとも清々しい気持ちで初日の入りを見に行くことになった。この楽しい旅も最終日となり、海に向かう足取りは重く、前を歩く娘の長くなって行く影を踏みながら進んだ。海岸沿いのカフェにたどり着く頃には、溶けた鉄のようなオレンジ色の初夕日が地平線に沈みかけ、我々が滞在していたアシラの空を染め始めていた。なんとなく、海岸の湿った砂に降り立ち、目を疑った。
ドラゴンが頭を出していた。
それは砂の上から盛り出た歪な石で、周りに落ちていた石までもが、竜のうねる体を表現し、まるでこっそりと姿を現したドラゴンそのものであったのだ。
こうして私は縁起良く、モロッコの旅とミッションを達成できたのである。