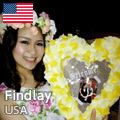起源は第二次世界大戦中にさかのぼります。ドイツからポルトガルへ逃れてきたユダヤ人一家、Davishon家の母親が、故郷で覚えたレシピを披露したのが始まりでした。
それは甘い小麦粉生地を揚げて丸く成形し、砂糖をまぶし、中に甘いフィリングを詰めたもの。ドイツでは「Berliner Pfannkuchen(ベルリナー・プファンクーヘン)」と呼ばれていました。最初は難民の仲間に分け与えるために作られていたものが、やがて誰でも買えるようになり、人気が高まりました。
難民たちは生計を立てるため、多くがカフェや菓子店で働き始め、その流れで、リスボンでもボーラ・デ・ベルリンが売られるようになります。やがて、ポルトガル人の菓子職人たちが独自のアレンジを加え、卵黄クリームを詰めるスタイルや、あえてクリームを入れないタイプなどが誕生しました。

それが、時代とともに変化し、今ではチョコレート、キャラメル、ストロベリー、ドゥルセ・デ・レチェ(ミルクジャム)、ヘーゼルナッツ、ココナッツ、レモンなど、さまざまなバリエーションが生まれ、お店ごとの味が楽しめるようになっています。とはいえ、ダヴィション夫人が作っていた本来のスタイルは、イチゴや赤いベリーのジャムを詰めた素朴なものだったそうです。調べてみたら、ドイツでは未だにジャム入りで、他にもブラジル、フランス、イタリアと様々な国で、多彩な味があるそうです。
ちなみに、先日初めてコーヒー味を試してみたのですが、定番の卵黄クリームよりも好みでした。

8月の真夏日、Carcavelos(カルカヴェロス)ビーチに行ったら、いました、いました!クーラーボックスを持ち歩き、「Olha! Bolinhaaaaa!」と叫ぶおじさんが!少し雑用をしている間に、どこかに移動してしまったみたいで、また逆方向に歩いて来るのを待つことに。少しすると、先ほどのおじさんと同じような格好で、同じように大声を張り上げているお兄さんがやってきました。おじさんと交代したのか聞いてみると、おじさんはクーラーボックスが空になり、補充しに行ったと。衛生面も考え、大量には持ち歩かず、定期的に補充する必要があるのです。炎天下の砂浜を歩き回りながら売り歩くのですから、それは非常にハードな仕事です。実際、近年ではビーチでの販売者が減ってきているともいわれています。とはいえ人気は衰えることなく、夏のピーク時には一日に数百個が売れることもあるそうです。
なぜ、ビーチでこれほど定番になったのでしょうか?
手で持って食べられるボーラ・デ・ベルリンは理想的なおやつです。砂浜でアイスクリームは溶けやすいですが、揚げパンは保存性が高く、日差しの強い海辺でも提供しやすかったというのもあります。また、海水浴のあとにぴったりの甘さだからです。
海に入ったあとは体に塩がつき、口の中にも塩気を感じます。その時に食べるボーラ・デ・ベルリンの甘さは、塩気と絶妙なコントラストを生み出し、より強い満足感を与えてくれるのです。しかも、揚げ菓子でありながら生地はふわっと軽く、パサつかないため喉も乾きにくく、砂浜で食べるには理想的。こうして「夏の海辺といえばボーラ・デ・ベルリン」という習慣が根づいていきました。

いまやポルトガルで最も愛されるお菓子のひとつとなったボーラ・デ・ベルリン。その人気の裏には、戦時下に祖国を追われた人々が故郷の味を持ち込み、それをポルトガルの人々が受け入れ、アレンジを重ねていった歴史が息づいています。
海辺でほおばるボーラ・デ・ベルリンの甘さには、避難民が伝えた記憶と、ポルトガルで育まれた物語が重なっているのです。