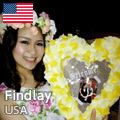ドゥオモの前でカメラを構え、スカラ座のチケットを手にし、ショーウィンドウの前で「かわいい!」と声をあげる、そんな光景がこの街の日常の一部だったのです。高級ブティックの商店街には大勢の日本人が訪れ、「それなのにすれ違い様に肩がぶつかることが一度もないのよ」とミラネーゼが感心して私に語ったものでした。ところが最近、街を歩いても日本人を見かけることがなくなりました。

調べてみると、それは気のせいではなかったのです。
かつて22万人を超えていたミラノへの日本人観光客は、2024年にはわずか6万8千人ほど。20年前の三分の一以下だと言います。この変化の背景には、円安と物価高、そして長くなった空の旅があります。東京からミラノへ向かう直行便は今、ロシア上空を飛べないため2時間ほど遠回りする。そのぶん航空券は高くなり、体への負担も大きい。「80〜90年代には年に3、4回ミラノに来ていた」と話す日本人シェフも、「今では円が弱すぎて難しい」と肩をすくめます。10年前は「この次の旅はイタリアへ」という具体的な夢が、今では「いつか、行けたらいいな」という漠然とした希望に変わっていて、日本人が遠のいてしまったような感じがします。
面白いのは、かつて“ミラノ常連”だった日本人が減る一方で、イタリア人が日本を目指していること。為替の追い風を受け、桜や富士山を見に行くイタリア人旅行者が年々増えているそうです。
ミラノは今、観光都市としてますます国際的に注目を集めています。ファッションウィーク、デザインウィーク、音楽イベントのために世界中から人が集まるけれども、日本人ビジネス客の滞在スタイルも変わりました。以前は五つ星ホテルで数日間過ごすのが当たり前でしたが、今ではAirbnbや格安ホテルに宿泊し、滞在も二日ほどで切り上げるケースが多いそうです。物価高は観光客だけでなく、ミラノ市民にも重くのしかかっています。ミラネーゼ自身を苦しめている生活費の高騰は、「価格を下げればいい」と簡単には言えない現実を生んでいます。

とはいえ、ミラノの魅力は消えたわけではありません。日本人の高級ブランド品を目当てとした旅はいつの間にか変化を遂げ、今では“体験の街”として訪れる人が増えているのではないでしょうか。高級ブランドよりも、路地裏の小さなビストロでの味わいや、デザイン地区のギャラリー、小さな職人工房をめぐる旅に惹かれる人たち。そうした静かな楽しみ方こそ、今の時代のミラノにふさわしいのかもしれません。
人の流れが変わっても、かつて日本人が憧れたミラノは、今もここに残っています。
夕暮れのトラムの音、ドゥオモの白い光。
そしていつの日か、またあの頃のように、日本語の「かわいい!」がこの街に響くことを、私は心のどこかで願っています。